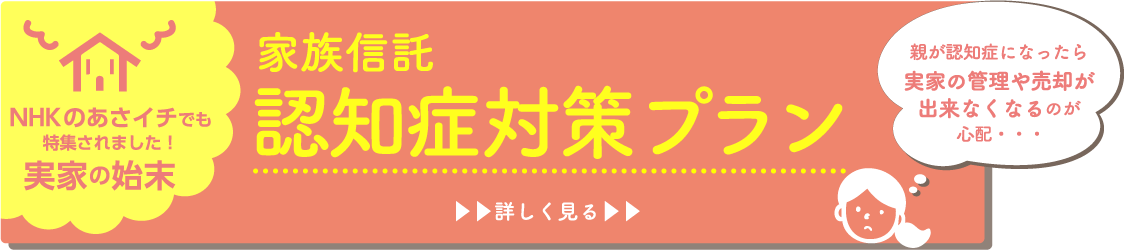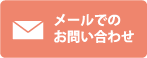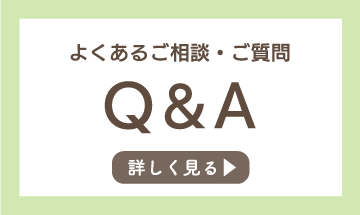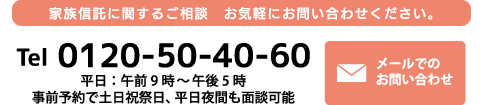ここ最近、ご相談が多いと感じるのが、いわゆる『親なき後問題』に関するものです。これは、障害者の子がいる親が自分の亡くなった後の障害者の子に関する財産管理や生活支援についての漠然とした不安や悩みのことです。
これは、親が亡くなる場合だけでなく、親の高齢化により、障害者の子の面倒を看てやれなくなったときにも、問題が顕在化します。内閣府が発行している令和2年度障害者白書によると、身体障害、知的障害、精神障害の3区分について、各区分における障害者数の概数は、身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)436万人、知的障害者(知的障害児を含む。以下同じ。)109万4千人、精神障害者419万3千人となっています。これを人口千人当たりの人数でみると、身体障害者は34人、知的障害者は9人、精神障害者は33人となる。複数の障害を併せ持つ者もいるため、単純な合計にはならないものの、国民のおよそ7.6%が何らかの障害を有していることになります。このうち、親なき後問題を抱えるのは、主に知的障害者と精神障害者となりますので、国民のおよそ4.2%となります。この他、ひきこもりの子を持つ親も数多くいますので、親なき後問題を抱えている方はかなりいるはずです。
この問題について、先日あった、ご相談を例に考えていきたいと思います。
お母様(70歳)の悩みは、知的障害をもつ長女(40歳)のことでした。長女は、グループホームで生活しており、財産管理はとてもできない状態でした。もう一人の子である長男(45歳)は、結婚して子供もおり、独立してやっておりますが、そんなに裕福でなく、長女の面倒を任せることは出来ないとのことでした。
お母様は当然、成年後見制度のことは当然ご存知でしたが、自分がしっかりしている間は、成年後見人を就けずに面倒を看ていきたいとのことでした。理由としては、専門家後見人が就いた場合に、長女が亡くなるまで報酬を払い続けなければならないことに抵抗があるということでした。
まず、こういったケースで問題になるのが、資産承継の問題です。
何も対策なしでいくと、お母様が亡くなると遺産分割協議が必要となりますので、必ず成年後見人の選任が必要になります。そうなると、遺産分割協議の為に選任した成年後見人が一生長女の財産を管理していくことになります。これを回避するには、遺言書で法律専門家を遺言執行者に選任することで、遺産分割協議をせずに資産承継をすることが確実に可能になります。
ただ、これだけでは、十分な対策ではございません。お母様の意思としては、障害を持つ長女に財産の多くを相続させて、一生困らないようにしたいと思っていたからです。と言いますのも、長女に財産を承継させることは、遺言書を作成し、遺言執行者を設けることで、可能となります。しかし、その長女の財産を、長女のために使える状態になっていないので、お母様の意思が実現できないからです。長女は、自分で相続した不動産を売却することも出来ませんし、財産管理自体もできないのです。
そのお母様が望む形を作り出す為に、使えるのも、民事信託・家族信託です。長男が協力的であることが必要条件になりますが、委託者(任せる人)をお母様とし、受託者(任される人)を長男とし、受益者を長女とする信託契約を締結することで、その想いが実現できます。
お母様が亡くなられた後に、定期的に施設利用料や生活費を長女に渡していくという内容にすることで、お金を長女の為に使える状態にすることができます。
この契約の形については、贈与税がかからないように、当初の受益者をお母様にすること(自益信託)で、お母様の扶養義務の範囲内で長女に生活費を支給することや、当初の受託者をお母様にして、お母様の健康状態によって受託者を長男に変えられる設計にした自己信託とする方法も検討できるかもしれません。
このケースでは、長男がいましたので、長男を受託者としましたが、障害のある子が一人っ子の場合、その子の財産は、亡くなった後、相続人がいないということで最終的に、国庫に帰属する可能性が高くなります。しかし、国庫に帰属させるのではなく、どうせなら、その一人っ子の面倒を看てくれた施設や団体に寄付したいというニーズは少なからずあろうかと思います。
そういう場合でも、民事信託・家族信託は有効です。委託者(任す人)をお母様、信頼できる親族を受託者(任される人)として、受益者を障害のある子として、信託契約を締結し、帰属権利者を施設や団体とすることで、自分の財産を国庫に帰属させることなく、希望する施設や団体に寄付することも可能になります。
また、障害をもつ子の為に、生命保険に加入しているが、いきなり多額の財産が入ることにより、悪意ある第三者に搾取されてしまったり、不必要なものに費やしてしまうことを心配されることもあろうかと思います。そんなときに使えるのが、生命保険信託となります。事前に支払われる金額や頻度を決めておくことができるので、定期的に少額の保険金を手にすることが可能になりますし、万が一障害を持つ子が亡くなった場合に、次に支払われる人の順番も決めることが可能です。重度の障害を持たれている場合には、結局お金を引き出せないので、成年後見人を選任しなければならないケースも出てきます。
このように、親なきあと問題について考えてみた時に、遺言書作成は必須として、民事信託・家族信託や後見、生命保険信託と、様々な選択肢を駆使、併用することで、親なき後の不安や悩みが解決することができるのではないかと思います。漠然とした不安や悩みを顕在化させること、すなわち、法律専門家に相談なさることから始めていかれることをお勧めいたします。


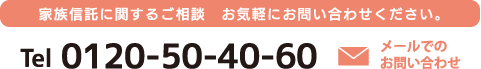
-683x1024.png)
-300x212.jpg)