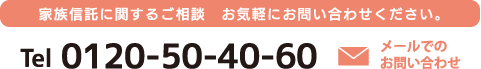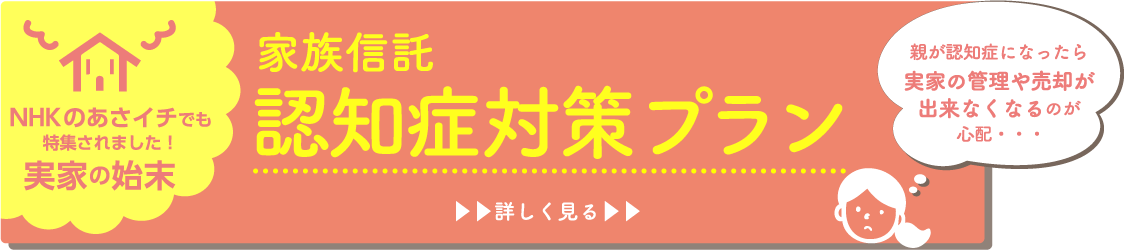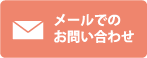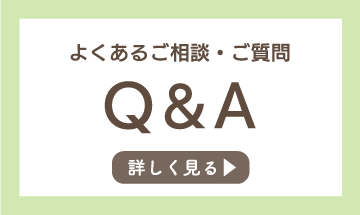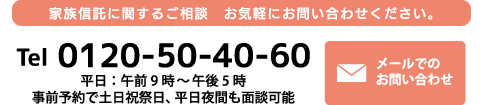昨日の続きです。
登録免許税法第7条第2項は、
要件① 信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合 であって
要件② 当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、
要件③ 当該受益者が当該信託の効力が生じたときにおける委託者の相続人であるとき
と規定していることから、その適用にあたっては、各要件を満たす必要があると考えられます。
委託者の地位については、帰属権利者に指定されている実子に、委託者の権利については、相続により承継されることなく消滅し、受益者の地位及び権利は、相続により承継されることなく消滅した上で、信託財産について、残余財産帰属権利者としている唯一の法定相続人である実子が取得するという内容の信託契約書の内容であった場合、委託者の死亡により、本件信託は終了し、帰属権利者として信託財産を取得するので、要件①を満たさないと思われるが、登録免許税法には、「受益者」の定義がないので、権利帰属者が受益者にあたるか否かについては、信託法の定義にて判断することになるはずです。
信託法では、「受益者」とは、受益権を有する者をいい、また、「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対して負う債務であって信託財産に属する財産の引き渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権及びこれを確保するために信託法に基づいて受託者その他の者に対し、一定の行為を求めることができる権利をいう旨規定されています。
そして、また信託法では信託が終了した場合においても、その清算が結了するまで信託はなお存続するものと擬制され、残余財産帰属権利者は、当該清算中受益者とみなされる旨規定されています。
すなわち、残余財産帰属権利者である乙は、本件信託の清算中、受益者とみなされますので、乙は登録免許税法の受益者に該当することとなります。
よって、本件登記は、本件信託の清算受託者である乙から、本件信託受益者乙に対する所有権移転登記であることから、要件①を満たすと解するのが相当です。
要件2は、本件特例の対象となる信託として、委託者のみが信託財産の元本の受益者となる信託であることをその要件としているところ、本件信託においては、甲が死亡するまでは、委託者が受益者であり、また委託者の死亡後は、委託者から委託者の地位を取得した乙のみが残余財産帰属権利者(受益者)であることから、同要件についても満たしていると解するのが相当です。
そして、乙は、本件信託契約の効力が生じた時における委託者である甲の相続人であることから、要件3についても満たすこととなります。
以上のとおり、本件登記については、本件特例の趣旨にも反しておらず、本件特例に係る各要件を全て満たしているものと解されることから、その適用があるものと考えられます。