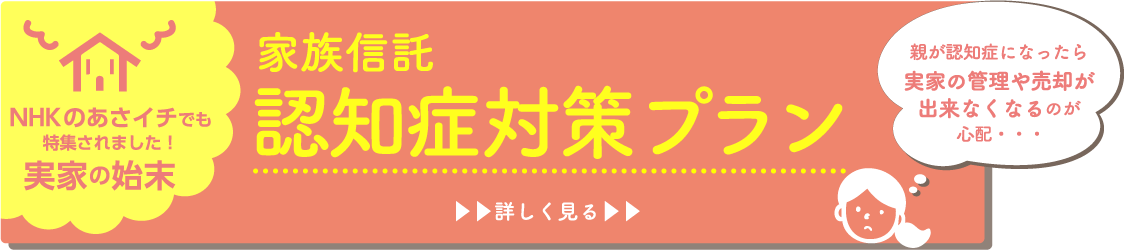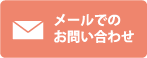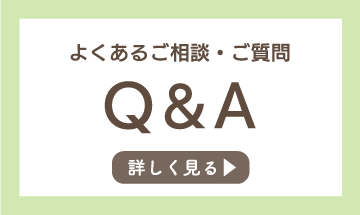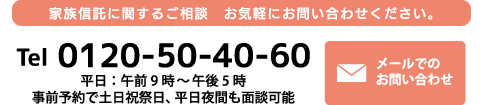お父さまご所有の土地建物に、お父さまが独りで暮らしておられます。そんなお父さまをもつお子様は、お父さまが認知症になり、独りで暮らしがままならない場合は、その家を売却して、介護費用、施設の費用を捻出し、施設に入所してもらおうと考えております。
お父さまも、その方針に異存がなく、今の間に不動産の名義を変えることを検討されご相談に来られました。いわゆる生前贈与です。
これは、まさに、家族信託、民事信託がピッタシの案件です。
生前贈与をしますと、贈与税、不動産取得税の税負担の問題が生じます。もちろん、将来、相続税が掛からないようなご家族であれば、相続時精算課税制度を使うことにより贈与税を非課税にすることはできますが、不動産取得税はかかってきます。
家族信託の場合は、委託者受益者をお父様にするのであれば、贈与税も不動産取得税もかからず、名義を移転することが可能です。
さらに、登録免許税も、贈与で名義変更する場合は、不動産の評価額の20/1000かかるところ、信託で名義変更する場合、土地は3/1000(令和3年3月31日まで)と建物4/1000の税率ですみます。たとえば、土地が1000万建物が500万の家であれば、贈与であれば、30万円の登録免許税が掛かるところ、信託であれば、5万円の登録免許税ですみます。
介護費用捻出の為の不動産売却であれば、認知症になった段階で、成年後見人を選任しても可能なケースかとも思いますが、急に、くも膜下出血などで倒れて判断能力が無くなる場合はあきらかでしょうけど、徐々に認知症の症状が進んでいくようなケースの場合、お父さまの管理ができるかできないか分からないような状態がしばらく続くことを回避する為にも、迅速に管理、処分の動きをとることができる家族信託、民事信託は有用の選択肢だと思います。
違う方策を依頼されに来られるお客様が、家族信託・民事信託の選択肢もありますよっていうお話をきいて、その選択を取られるケースは多いです。
その選択肢を知らず、もしくは、その選択肢を提案もせず、生前贈与として受任してしまう専門家もいると思います。
上記の通り、選択肢を知っているかどうかで、費用も手間も将来の安心も、大きく変わってきます。
その選択肢を提示させて下さい。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。


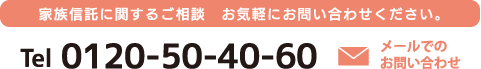
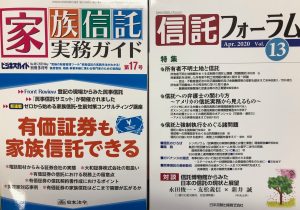
-212x300.jpg)

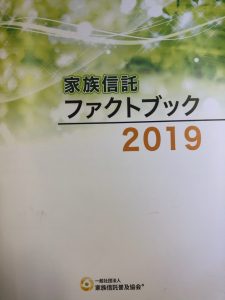 当事務所も会員となっております家族信託普及協会発行の本を紹介したいと思います。
当事務所も会員となっております家族信託普及協会発行の本を紹介したいと思います。